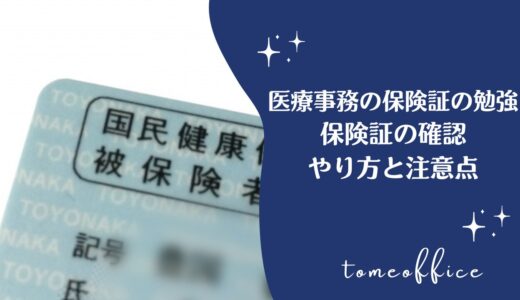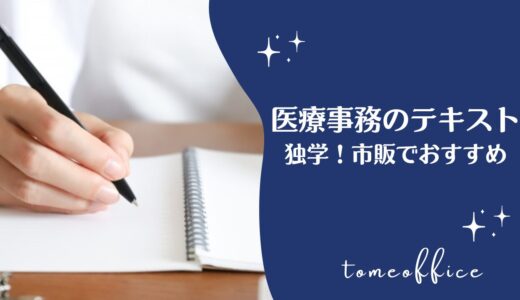本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
この記事で解決できるお悩み
こんな悩みを解決できる記事を用意しました。
レセプトが出来ないと医療事務ではない!と言われることもあるくらい、医療事務にとってはレセプト業務は大切です。
その理由は、病院やクリニックの収入のほとんどがレセプト業務で請求した報酬で成り立っているから。
医療事務の経験者の私が、記事の前半で『レセプト用語を簡単に説明』を解説し、
後半では『レセプト総括までやり方はどうやってするの?』と『レセプト返戻!国保から社保へ返戻再審査請求の処理』について紹介するので、参考にしてくださいね!
全学習内容がeランニングで学べる。
講義映像が充実。
オリジナルテキストがデジタルにも対応。
学習コンプリート動画や添削課題4回もwebからOK。
デジタルテキスト&webテスト有でスキマ時間に学習可能。
学習スケジュールを自動作成してくれる。
ポイント動画視聴などデジタル学習対応。
通学コースの授業に5回まで参加できる無料聴講制度有。
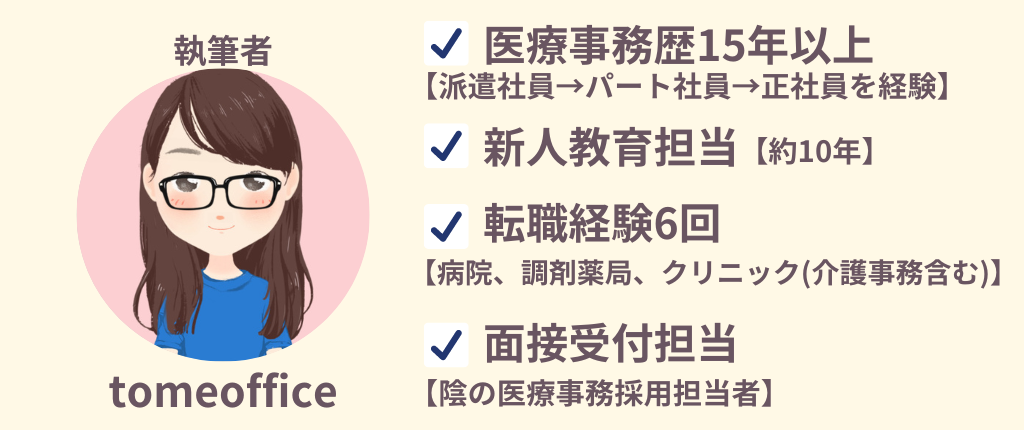
目次
レセプト用語を簡単に説明
 tomeoffice
tomeoffice
そんな方の為に、わかりやすい文章で紹介しますね。
他にも???のことがあるかもしれませんが、1つずつ解説していきます。
①診療報酬明細書(レセプト)とは?
イメージして欲しいのですが
- 体調が悪くて保険証を持って医療機関のドアを開けました
- 医療機関の受付で保険証を提示して、保険診療で診療を受けました
- 患者自己負担分を医療機関でお支払いをしました
- 医療機関が保険者負担分を請求する明細書が、診療報酬明細書(レセプト)
それを、月ごと診療報酬明細書を作成し、保険者に提出をして、医療機関の報酬を得ます。
- 患者が毎月支払いをしいている保険者に、当医療機関は、保険診療を行える医療機関の手続きをしております。
- 保険医の登録も行っております。
- 〇〇保険者さんの被保険者証を持参された受診者の診療を保険医が行いました。
- 報酬を得たいので、細かく書いて提出しますので、〇〇保険者さん、当医療機関に報酬をお願い致します。
と、作成し、提出する明細書がレセプトです。
②社会保険診療報酬支払基金はどんなところ?
- 医療機関から提出された診療報酬請求書の審査を行っています。
- 保険者(全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合等)から医療機関への診療報酬の支払仲介を行っています。
また、生活保護も支払基金に提出です。
 tomeoffice
tomeoffice
③国民健康保険団体連合会はどんなところ?
- 医療機関から提出された診療報酬請求書の審査を行っています。
- 保険者(市区町村及び国保組合)から医療機関への診療報酬の支払仲介を行っています。
- 国保連は、国民健康保険の持つ地域医療保険としての特性を生かすために各都道府県に1団体、計47団体設立されています。
 tomeoffice
tomeoffice
④審査支払機関はどんなところ?
- 社会保険診療報酬支払基金
- 国民健康保険団体連合会
2つあります。
医療機関と保険者の間には「審査支払機関」があります。
医療機関からの診療にかかわる医療費の請求が正しいかを審査した上で保険者へ請求し、保険者から医療機関への支払いの事務なども代行します。
 tomeoffice
tomeoffice
⑤診療報酬請求書とは?
診療報酬請求書とは、診療報酬明細書(レセプト)を作成し、社保と国保に分け、月ごとにまとめた件数、実日数、点数を集計した表=総括のことです。
全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合等の保険者をまとめて、診療報酬請求書を作成し、社会保険診療報酬支払基金へ提出します。
また、市区町村及び国保組合の保険者をまとめて、診療報酬請求書を作成し、国民健康保険団体連合会へ提出します。
 tomeoffice
tomeoffice
医療事務の基礎知識がない場合は、診療報酬に関する本を読んで勉強するのもおすすめ!
下記のリンクで紹介していますので、参考になさってください。
全学習内容がeランニングで学べる。
講義映像が充実。
オリジナルテキストがデジタルにも対応。
学習コンプリート動画や添削課題4回もwebからOK。
デジタルテキスト&webテスト有でスキマ時間に学習可能。
学習スケジュールを自動作成してくれる。
ポイント動画視聴などデジタル学習対応。
通学コースの授業に5回まで参加できる無料聴講制度有。
医療機関がレセプトを提出すると何処から診療報酬を得られるの?
 tomeoffice
tomeoffice
1つずつ解説していきます。
①患者さんと保険者と医療機関で診療報酬が支払われる仕組み
| 患者 | 保険料を支払う→ | 健康保険協会、健康保険組合、共済組合、市区町村など |
| ←保険証を交付する |
| 患者 | 診療報酬の自己負担分を支払う→ | 医療機関 |
| ←保険診療を行う |
患者の窓口負担最大3割
患者さんは来院の度に、病院やクリニックは領収証を作成し窓口負担最大3割のお金を請求しお支払いして頂く。
②医療機関と審査支払機関で診療報酬が支払われる仕組み
| 医療機関 |
診療報酬請求書を請求する→ 診療報酬明細書(レセプト)を提出する→ |
審査支払機関 |
| ←診療報酬を支払う |
健康保険の保険者負担7割以上
患者さんが来院の度に、保険者からお金を受け取ることができません。
請求作業が大量になり、手間もかかります。
そのため、1ヶ月ごとまとめて請求を行う仕組みになっています。
医療機関が、健康保険協会、健康保険組合、共済組合、市区町村などから、診療報酬を受け取る場合は、「社会保険診療報酬支払基金」「国民健康保険団体連合会」の「審査支払機関」に診療報酬請求を行います。
この時に提出をするのが「診療報酬請求書」「診療報酬明細書(レセプト)」の書類です。
診療報酬明細書(レセプト)には、患者さんの氏名、生年月日、保険者、医療機関名、診療を行った傷病名、診療行為の内容、処方した薬などに応じた診療点数(1点=10円の診療費用)1ヶ月分まとめて記載されています。
③審査支払機関と保険者で診療報酬が支払われる仕組み
| 審査支払機関 | 診療報酬明細書(レセプト)を提出する→ | 健康保険協会、健康保険組合、共済組合、市区町村など |
| ←診療報酬を支払う |
審査支機関は、診療報酬請求書とレセプトの内容を審査し、請求内容に不備がなければ、健康保険協会、健康保険組合、共済組合、市区町村などに診療報酬を請求します。
健康保険組合などは、審査支払基金の請求に応じ、審査支払基金を通じて、医療機関に診療報酬を支払う仕組みになっています。
医療事務の基礎知識がない場合は、診療報酬に関する本を読んで勉強するのもおすすめ!
下記のリンクで紹介していますので、参考になさってください。
しかし、自分で勉強するのが難しい場合は、医療事務通信講座を受講した方が理解が深まります。
医療事務通信講座は、無料資料請求出来るので、比較検討してみよう!
全学習内容がeランニングで学べる。
講義映像が充実。
オリジナルテキストがデジタルにも対応。
学習コンプリート動画や添削課題4回もwebからOK。
デジタルテキスト&webテスト有でスキマ時間に学習可能。
学習スケジュールを自動作成してくれる。
ポイント動画視聴などデジタル学習対応。
通学コースの授業に5回まで参加できる無料聴講制度有。
レセプト業務とは?何をするの?

レセプト業務とは、診療報酬請求書と診療報酬明細書(レセプト)を作成し、審査支払機関に提出する業務です。
また、診療報酬とは、診療に要した費用のことで、診療報酬点数表に基づいて点数計算を行います。
そして、医療費は、診療報酬点数1点を10円として領収金額を計算します。
日本では国民皆保険制度という公的な保険制度があります。
その制度は、保険加入者が医療機関で保険診療の診察を受ける時は、保険証を提示すれば、最大で医療費の3割を患者が負担し、残りの7割は、社保(健康保険組合など)や国保(市区町村など)の健康保険の保険者が負担する仕組みになっています。
その為、医療機関の収入は、患者が窓口で支払っている医療費だけで成り立っているわけではありません。
患者自己負担3割の保険証の場合
患者自己負担3割+保険者負担分7割=医療機関の収入10割
保険者負担分7割の医療費を請求する業務がレセプト業務です。
患者さんが1月10日と1月31日に受診をした場合
医療事務通信講座は、無料資料請求出来るので、比較検討してみよう!
 tomeoffice
tomeoffice
全学習内容がeランニングで学べる。
講義映像が充実。
オリジナルテキストがデジタルにも対応。
学習コンプリート動画や添削課題4回もwebからOK。
デジタルテキスト&webテスト有でスキマ時間に学習可能。
学習スケジュールを自動作成してくれる。
ポイント動画視聴などデジタル学習対応。
通学コースの授業に5回まで参加できる無料聴講制度有。
レセプト総括までやり方はどうやってするの?

レセプト業務・レセプト作成は、一般的に毎月月末から10日まで集中的に行われることが多い。
その理由は、審査支払機関へ診療報酬請求書と診療報酬明細書(レセプト)の提出期限が、診療行為を行った翌月の10日までと定めているからです。
例えば1月分は2月10日に提出します。
診療報酬は原則として、オンラインでの請求が義務付けれています。
1つずつ解説していきます。
①診療情報を電子カルテやレセコンに入力(毎日の業務)
 tomeoffice
tomeoffice
診療録(カルテ)の1号用紙→レセプトの一番上の部分
診療録(カルテ)の2号用紙と3号用紙→病名より下のレセプトの摘要欄の部分
電子カルテやレセコンに記録されたら、そのままレセプトに反映されます。
その主保険がレセプト請求先。
保険証が変更になっている場合は、主保険の記載を変更しなければ、以前の主保険先に、レセプト請求することになるので、注意が必要。
その保険指定がレセプト請求先。
主保険が変更になっている場合、割合変更になっている場合、公費の変更になっている場合、頭書きの保険変更を行わないと、以前の主保険先に、レセプト請求をすることになるので、注意が必要。
2号用紙の記載は、医師が行います。
後から、記載が出来ないように、日付印は詰めて押します。
2号用紙の記載の内容が、レセプト請求出来るものを、医療事務がみて判断をし、点数計算をするやり方を医療事務講座で勉強します。
医師が患者を選び診察を開始すると、2号用紙の画面が、医師の端末に開きます。
2号用紙の記載は医師のみ行えるので、医師指定になっている。
2号用紙で、レセプト請求出来るものを、処置行為に入力をされなければ、レセプト請求が出来ません。
2号用紙の記載の内容が連携して3号用紙に移るので、医師に2号用紙で算定、入力出来ていないものは、医師に確認が必要。
会計カードは医療事務講座で書き方を勉強をします。
過去のカルテをみて、同月算定不可のものを算定されていないか?
医療事務講座で勉強した会計カード、同日算定不可、同月算定不可、加算算定可能、など、頭の中で考え、レセプトをイメージして計算をしていく。
レセプトの内訳になります。
患者さんが加入している保険者が医療機関に払う報酬以外のものを、患者の自己負担の分を、領収証に記載されているか?確認をし、患者さんを呼び、お支払いをお願いする。
外来患者さんの場合は、来院の度に行い、入院患者さんの場合は、月に何回かの精算の度に行います。
電子カルテやレセコンで領収証を作成して、発行した領収証の金額は患者負担分です。
残りの分を月がかわったら保険者に請求します。
実際に、医療事務の新人さんは「レセプトをいつまで経ってもやらせてもらえない!」と仰る方も多いです。
しかし、日中の仕事内容がそのままレセプトになっているので、カルテ作成も、保険証確認も、会計で患者さんからお支払いをお預かりすることも、全てレセプトに関わっていますよ。
 tomeoffice
tomeoffice
②レセプト作成 (毎月1日~10日)
月がかわったら、電子カルテやレセコンに入力された1ヶ月分の診療報酬の点数を確認してレセプトを作成します。
電子カルテやレセコンが1ヶ月分の診療内容、診療報酬を自動的に集計して出力してくれますが、そのやり方を覚えないと、レセプト作成は出来ません。
今はエコで、紙出力をせず、PCのプレビューで作成をし、必要によって、出力をする場合が多いですね。
 tomeoffice
tomeoffice
③レセプト点検(毎月1日~10日)

レセプト業務のメインの仕事です。
実際に、電子カルテやレセコンに入力されている情報が正しいとは限りません。
PCを操作をするのは人ですので、ミスもします。
医療事務が入力を間違える可能性もありますし、医師の診療内容や処方薬と傷病名の整合性がとれているか?確認が必要!
今は、レセプト点検ソフトがあり、請求漏れを教えてくれるものもありますが、あくまでもソフトですので、人の目で見た方がよいことも多いですよ。
 tomeoffice
tomeoffice
患者を受付し、氏名、生年月日、保険証の確認(保険者の確認)それを間違えなく登録する。
保険者に患者が来院し診療を行ったので報酬を請求するのがレセプト業務です。
報酬がはいらない(返戻)のほとんどは、保険証の入力ミスのことが多いので、気を付けて入力を行いましょう!
医療事務のミスの改善策の詳細は、下記のリンクで紹介していますので、参考になさってください。
また、レセプト点検の主な仕事内容は、病名の記入漏れの確認業務です。
 tomeoffice
tomeoffice
医師は患者の訴えを聞き、疑って検査をし、症状にあった薬を処方し、診断、病名をつける。
この診療を1日何十人と間違えずに、おこなうことが医師の主な仕事になります。
医師も人間なので、何か抜けてしまうこともあるので、後で確認できるように付箋を付けてわかるようにしておきましょう!
実際に、レセプトの上から1つ1つ漏れがないか?多く算定しすぎていないか?決められた枠で請求出来ているか?チェックしていきます。
でも、本当に大切なのは、何処に請求するかで、中身がいくら完璧に出来ても、請求先が違っていたら、医療機関に報酬は入りません。
なので、医療事務の保険証確認は、立派な医療事務のレセプトの仕事内容の1つですので、自信を持って仕事を行って下さいね。
 tomeoffice
tomeoffice
保険証確認の仕方と注意点は、下記のリンクで紹介していますので、参考になさってください。
④医師に確認(毎月1日~10日)
レセプト点検・確認業務のなかで、記載されている傷病名と診療内容などに整合性が取れない場合は、医師に確認を行う必要があります。
病名を診断するのは、医師の仕事で、医療事務は、おかしいな?と、思うことを医師に確認をするのが仕事です。
診療の内容によって、必要な場合、何故、このような治療を行った理由をレセプトに記載する為、医師に症状詳記の記載をお願いします。
在宅の指導料などは、コメントを細かく入力する場合があり、医師が行う場合と医療事務が行う場合、医療機関によって違いますので、確認が必要ですよ。
また、生活保護の交付番号など、コメントが必要な場合は、医療事務がコメントを入力します。
生活保護に関する医療事務の仕事内容は、下記のリンクで紹介していますので、参考になさってください。
医師と医療事務が、協力して返戻や査定をされないように、気を付けてチェックをする。
医師に確認し修正が必要な場合、電子カルテの場合は医師に修正をお願いします。
レセコンの修正が必要な場合は、医療事務が修正を行い、最終確認を医師にお願いします。
医師の確認が終了したら、レセプト作成は完了です。
検査を行っているのに検査病名が見当たらない場合
 医療事務
医療事務
カルテをみて検査を行い結果が出て、患者さんに説明をしている場合
 医療事務
医療事務
先月の急性病名がレセプトに記載されている場合
 医療事務
医療事務
医療事務の勉強の内容は計算方法が主ですが、実際は計算もしつつ、病名もれのチェックが主です。
⑤診療報酬請求書の作成(毎月1日~10日)
 tomeoffice
tomeoffice
通常のレセプト請求の場合「社会保険診療報酬支払基金」と「国民健康保険団体連合会」2か所に診療報酬請求書を作成します。
今は、電子カルテやレセコンの操作をすれば、自動で計算をし、作成してくれますよ。
届け出をした印鑑を押して提出の準備をし、控えのコピーを取り、ファイリングします。
⑥審査支払機関に提出(毎月1日~10日)
 tomeoffice
tomeoffice
提出されたレセプトと診療報酬明細書は、審査支払機関で厳重な確認作業が行われます。
もし、レセプトの記載内容に誤りがあると、審査支払機関からレセプトが病院やクリニックに差し戻され(返戻)、診療報酬点数が減点されたり(減額査定)がおこることがあります。
返戻された場合は、レセプトを精査・修正し、再提出をしなければなりません。
⑦レセプト返戻と査定があることもある
レセプト返戻と査定の違い
| 返戻 | 査定 | |
|---|---|---|
| どのような場合に 行われるのか? |
レセプトの内容に確認が必要な場合 | 請求が不適当と判断した場合 |
| どのようにわかるのか? | レセプト自体を差し戻す | 不適当な項目を修正(減額・減点など)増減点連絡書が届く |
| 報酬は得られる? | レセプト自体が戻されたので報酬は得られない | 減額・減点分が差し引かれて支払われる |
| 再請求は? | 修正すれば、再請求は可能で、審査が通れば、報酬も得られる | 納得が出来なければ「再審査・取り下げ依頼書」を書き提出する |
 tomeoffice
tomeoffice
レセプト返戻とは
レセプトの記載内容に不備や誤りなどがあり、レセプトの内容に確認が必要な場合は、審査支払機関や保険者から、提出した保険医療機関にレセプトが差し戻されます。
その為、病院やクリニックなどの医療機関は内容を精査、修正し、再提出することになります。
その後、再提出で適切だと判断されれば、医療機関に報酬が入りますよ。
ただ、当月に見込んだ報酬を得られないので、医療機関の人件費などの支払いに影響を及ぼすこともありますね・・・
 tomeoffice
tomeoffice
レセプト返戻の多くは保険証の入力ミス
ほとんどの場合は保険証の不備が多いです。
- 保険資格喪失後の受診
- 保険者番号・記号・番号の不備
- 氏名の不備
- 生年月日の不備
- 男・女の不備
何処に、診療報酬を請求すれば良いのか?該当者なしで、わからないので、レセプト自体が戻されます。
その為、保険証を忘れた場合は、自費精算にする。
 tomeoffice
tomeoffice
レセプト点検に関する詳細は、下記のリンクで紹介していますので、参考になさってください。
レセプト査定とは
レセプトに記載されている内容を不適切であると判断した場合、審査支払機関や保険者から、提出した保険医療機関にレセプトの項目内容を修正(減額・減点など)し、調整した額で支払われることをいいます。
その為、査定は実施した医療行為の報酬が得られないので、医療機関にとっては厳しい制度です。
 tomeoffice
tomeoffice
査定された内容
- 何か月に1度しか算定出来ないもの
- 初回コメントが入っているのに、初回ではない場合
- 月に1回しか算定出来ないのに、2回算定している場合
- 初診料を算定してから1ヶ月以上経過しないと算定出来ないのに算定してしまった場合
- 同月算定不可のもの算定してしまった場合
- 薬の長期処方
- 入院費で算定しているのに外来でも算定していたら減点されます
- 退院から1ヶ月経過しないと算定出来ないものを退院直後に算定していたら減点されます
 tomeoffice
tomeoffice
医療事務の基礎知識がない場合は、診療報酬に関する本を読んで勉強するのもおすすめ!
下記のリンクで紹介していますので、参考になさってください。
しかし、自分で勉強するのが難しい場合は、医療事務通信講座を受講した方が理解が深まります。
医療事務通信講座は、無料資料請求出来るので、比較検討してみよう!
全学習内容がeランニングで学べる。
講義映像が充実。
オリジナルテキストがデジタルにも対応。
学習コンプリート動画や添削課題4回もwebからOK。
デジタルテキスト&webテスト有でスキマ時間に学習可能。
学習スケジュールを自動作成してくれる。
ポイント動画視聴などデジタル学習対応。
通学コースの授業に5回まで参加できる無料聴講制度有。
レセプト返戻!国保から社保へ返戻再審査請求の処理

国保から社保へ修正を行う場合は、診療録(カルテ)の1号用紙の保険登録が違っているので、そこから修正を行います。
診療録(カルテ)は、1号用紙、2号用紙、3号用紙、セットです。
例「1年10月分、国保から社保加入をされていた。電子カルテやレセコンの保険確認画面を確認したら、患者さんから提示されたのは、国保だった。」
医療機関は保険確認業務を行っていたので、落ち度はない場合、レセプトの返戻に、保険者番号、記号、番号、本人家族の内容の記載がある場合が多いです。
しかし、社保は支払基金へ提出する。国保は国保連合会へ提出する。
その為、国保から社保へ加入していたレセプトは医療機関に返戻されることがほとんどです。
保険証のレセプト返戻は、診療録1号用紙の記載が違っていた為なので、1年10月分の1号用紙の保険者を修正する必要がありますね。
返戻は過去のものなので、過去の日付まで戻って保険者の登録を行わないと、レセプト返戻の修正が出来ないので注意が必要です!
 tomeoffice
tomeoffice
診療録1号用紙、2号用紙、3号用紙はセット
1年10月分の1号用紙の保険者を変更する作業をする
1号用紙、2号用紙、3号用紙はセットなので
2号用紙の診療内容も保険者を変更する
3号用紙の会計カードも保険者を変更する
病名、初再診、処置行為、検査、処方内容などを、社保の保険者に移動します。
国保のデーターの総点数が0になり、請求なしになっているか?確認します。
国保の返戻されたレセプトの総点数と、社保の領収証に記載されている領収証の総点数が一緒か?確認します。
一緒であれば、社保にデーターが移ったことになります。
あっていれば、国保の保険者番号に記載されていた内容が、社保の保険者番号に移ったことになります。
電子カルテやレセコンのやり方をみて、処理を行わないと、せっかくデーターを移したのに、提出が出来ません。
提出が出来ないと、医療機関に報酬が入りません。
修正を行ったら、返戻の総括表を作成し、レセプト返戻再請求の処理を行います。
医療事務の基礎知識がない場合は、診療報酬に関する本を読んで勉強するのもおすすめ!
下記のリンクで紹介していますので、参考になさってください。
しかし、自分で勉強するのが難しい場合は、医療事務通信講座を受講した方が理解が深まります。
医療事務通信講座は、無料資料請求出来るので、比較検討してみよう!
全学習内容がeランニングで学べる。
講義映像が充実。
オリジナルテキストがデジタルにも対応。
学習コンプリート動画や添削課題4回もwebからOK。
デジタルテキスト&webテスト有でスキマ時間に学習可能。
学習スケジュールを自動作成してくれる。
ポイント動画視聴などデジタル学習対応。
通学コースの授業に5回まで参加できる無料聴講制度有。
まとめ
- レセプト業務とは、診療報酬請求書と診療報酬明細書(レセプト)を作成し、審査支払機関に提出する業務
- 医療費は、診療報酬点数1点を10円として領収金額を計算する
- レセプト業務・レセプト作成は、一般的に毎月月末から10日まで集中的に行われることが多い
- その理由は、審査支払機関へ診療報酬請求書と診療報酬明細書(レセプト)の提出期限が、診療行為をを行った翌月の10日までと定めているから。
- 国民健康保険から社保へ変更した場合は、診療録1号用紙から修正をし、社保のレセプトを作成する必要がある
あくまでも私の経験上ですので、ご了承ください。
全学習内容がeランニングで学べる。
講義映像が充実。
オリジナルテキストがデジタルにも対応。
学習コンプリート動画や添削課題4回もwebからOK。
デジタルテキスト&webテスト有でスキマ時間に学習可能。
学習スケジュールを自動作成してくれる。
ポイント動画視聴などデジタル学習対応。
通学コースの授業に5回まで参加できる無料聴講制度有。
関連記事